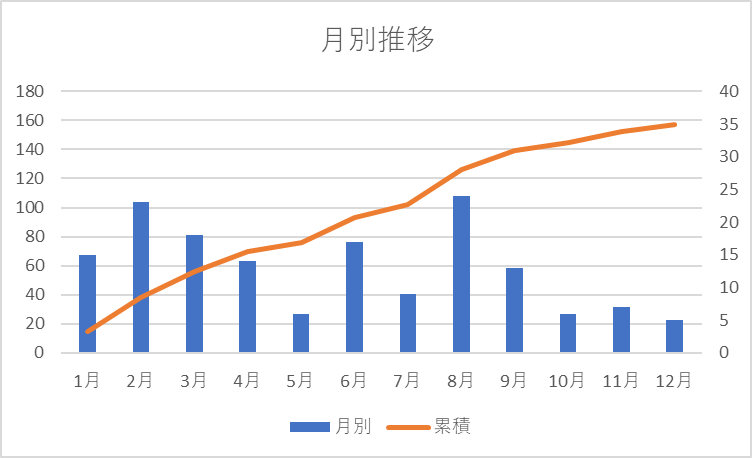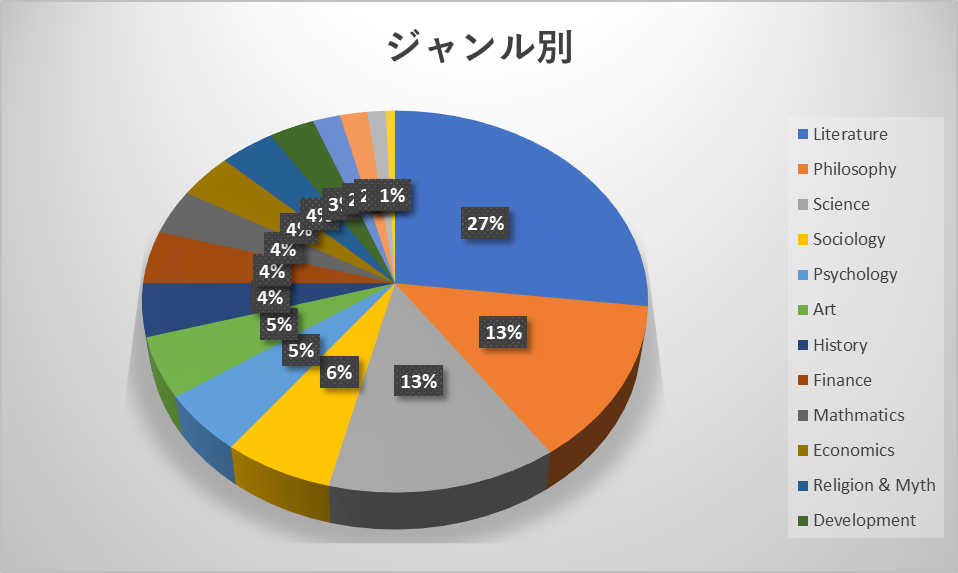2021年も終わるので、改めて今年1年間の読書歴を振り返ってみたいと思います。
2021年から、Notionを利用して読書録をつけ始めました。前記事では全体的な振り返りを行ったので、本記事ではテーマ別に印象に残った本を紹介していきます。
9. 社会学、人類学
経済学畑にいて社会学はあまり触れてきませんでしたが、現代社会を理解する上で欠かせない教養として、今年になって10冊以上読みました。
①『消費社会の神話と構造』ジャン・ボードリヤール
社会学の1冊目はもはや古典となった名著です。高名な社会学者が消費社会の本質について語ります。以下は読書録からの引用です。
全ての消費者は自分で望み、自由に消費を行っていると信じているが、実は消費という記号に従い、差異化を強制されているに過ぎない。(中略) 現代社会は豊かであると同時に、永遠の渇望を宿命づけられているかのようだ。(中略) 本質的に「個々の欲求が生産の産物(=生産によって真の欲求が歪められている)」なのではなく、「欲求のシステム自体が生産のシステムの産物」なのだ。 消費者は自由に商品を選択していると信じている。しかし実際は資本主義システムによって生み出された構造的窮乏の中で、システムによって差異化された記号を消費し、作られた欲求を満たしているに過ぎないのである。
本書で提示されたボードリヤールの差異的消費の理論は、同じような機能の商品が繰り返し投入され、莫大な広告費をかけて販売されている現代においても、決して色褪せてはいないと感じます。
②『THE LONELY CENTURY』ノリーナ・ハーツ
社会学の2冊目は現代社会の病理を扱った本。コロナ禍もあり、現代ほど人が孤独になった世紀はありません。なぜ人は孤独になってしまったのか、その運命を変えるには何をするべきかが語られます。以下は読書録からの引用です。
21世紀ほど人類が孤独になった世紀はない。そしてそれは新型コロナの感染拡大及びロックダウンによって加速している。(中略) 様々なデータが示すように、現代ではどの先進国も孤独を感じる人の割合が非常に高い。孤独は個人・社会に対して非常に悪い影響をもたらす。(中略) 現代人が孤独なのではコロナ禍で始まったことではなく、構造的な問題がある。(中略)都会は儀礼的無関心の場であり、人は孤独になりやすい。農村で成立していた地域社会は人の流動性が高い都市では成立せず、人はコミュニティを持たない状況に追い込まれてしまう。デジタル化とコンタクトレスの都市設計は、住民同士の何気ない交流の頻度を低下させてきた。スマートフォンとSNSは人と常時つながっているように錯覚させるが、対面でのコミュニケーションにおける共感力を低下させ、質の高い交流機会を奪っている。(中略) 孤独の世紀を逆転するには何をすればよいのだろうか。それは、孤独に向けた構造的要因―伝統的な家族やコミュニティを崩壊させ、過度な個人主義と効率至上主義を生んだ新自由主義―を修正することだ。(中略) 21世紀を孤独の世紀ではなく、誰もが誰かと繋がっていると感じられる世紀にしたい、筆者の想いには非常に共感する。
ともすれば孤独になりがちな現代、人の繋がりは経済効率性よりもはるかに大事であると改めて思います。
③『二重に差別される女たち』ミッキ・ケンダル
社会学の3冊目はアメリカ黒人女性の置かれた苦しい状況を語った本。以下は読書録からの引用です。
この文章は「わたし」の怒りそのものだ―。 本書の著者はアメリカに暮らす黒人女性。近年フェミニズム運動が盛んになっているが、その「連帯」はあくまで白人女性にとどまっていて、黒人女性が排除されていることを筆者は糾弾する。(中略) 筆者はそんな「2重の差別」を自らの生々しい経験に基づいて語っていく。筆者は貧しい「フッド」に生まれたが、偶然にも十分な社会的地位を手に入れることができた。しかし、一歩間違えれば全く人生の方向性が異なっていたであろう出来事に何度も遭遇している。(中略) 本書は驚くほど「わたし」という言葉が多用されている。それによって、本書は人の心を打つ強い力を持っている。 「客観的であるべし」ということ自体、実は強者の抑圧の手段に過ぎないのかもしれない。そして、社会を変えるのはきっと、客観的ぶって何も言わない傍観者ではなく、「怒れるわたし」なのだ。
これほど「わたしの怒り」に満ちた本を読んだことはありませんでした。社会を変えるのは冷静な傍観者ではなく、声を上げる当事者なのだろうと強く感じます。かなり衝撃的な内容でした。
④『21世紀の文化人類学』前川啓治他
文化人類学からも1冊だけ紹介します。現代の文化人類学を概観した本。以下は読書録からの引用です。
21世紀の文化人類学はどこに向かうのか―それを何人かの文化人類学者が語る。(中略) フィールドワーカーは所属する文化や言語によって思考や表現が規定されている。そんなフィールドワーカーが、調査先の文化を相対的に見る(=超越的視点を持つ)ことは根源的に不可能だ。(中略)ポストモダンの影響を受けた1980年代の『文化を書く』論争の中で、「民族誌」は客観的たりえないという自己批判がなされる。この後、一般的理論を語れない文化人類学は知的世界をリードできず、衰退していく。(中略) 一方で、「われわれ」の思考を相対化する文化人類学の価値は、現代において非常に高まっているはずだ。 文化人類学が自己批判を自ら超克し、知的世界をリードすることが、社会科学ひいては人類に大いに貢献することだけは間違いないだろう。
存在論的転回や、時間性の超越など、本書で展開される議論は難解で、全てを理解できているわけではありません。それでも文化人類学的な考え方の重要性は強く感じました。
10. 哲学、思想
最後は哲学・思想系です。ここに分類するのが適切なのか分からないものもありますが、20冊程度読みました。
⑤『反脆弱性』ナシーム・ニコラス・タレブ
哲学、思想の1冊目は世界的知性であるタレブが、自身の思想を語った書です。以下は読書録からの引用です。
ブラックスワンの作者タレブが、Antifragile(反脆弱性)の概念を語った書。圧倒的な知性と教養を併せ持つ筆者が自由に書きたいことを書いているが、メッセージは一つ。「反脆弱になれ」と。変動やリスクによって大きなダメージを受けるのが”脆い”、変動やリスクの影響を受けづらいのが”頑健”だとすれば、”反脆い”ものは、変動やリスクによってかえって利益を得るのだ。(中略) 本書は全体を通して圧倒的な説得力がある。タレブの言う”反脆さ”という概念は、確かなレベルで自身の思考の中にも刷り込まれてしまった。
変動やリスクによって打撃を被る脆い存在になるな、それらによってかえって利益を得る反脆い存在になれ、と。タレブ流の思考術は、生きていく上でかなり重要な示唆を与えてくれるように思います。
⑥『Humankind 希望の歴史』ルドガー・ブレグマン
哲学、思想の2冊目は最近話題の希望に満ちた書です。人類は根源的に善良だという新しい人間観を高らかに宣言しています。以下は読書録からの引用です。
筆者は説く、人間の本質は善であるーと。(中略) 今まで数々の言説によって、人間の今まで数々の言説によって、人間の本質は悪だと主張されてきた。しかし、人間の本質を悪だとする主張は事実を正しく捉えていないし、予言の自己成就のメカニズムを通じて、人間を実際に悪にしてしまうという意味において最悪なのだ。(中略)人間性を貶めることによる悪のループから人間を救うためには、こうした希望に満ちた主張が、今最も求められているのではないだろうか。(中略) 本書ではこの主張を裏付けるため、ヒュドラのように恐ろしい「ベニヤ説」―人間の本質は悪だという「神話」―を一つずつ反証していく。(中略) 人が人に思いやりと信頼をもって望めば、きっと向こうもそれに答えてくれる。第1次大戦の塹壕において、クリスマスに自然発生した休戦のように。相互不信の運命を変えようではないかーと。(中略) 少しでもすべての人がお互いを尊重し合える世界に近づくことを祈らずにはいられない。
人間に対して悲観的な見方が溢れる世界ですが、今求められているのはこうした楽観的な人間観だと思います。純粋に利己的な人間はほとんどおらず、ほとんどの人は誰かのために働きたいと思っているのではないでしょうか。人間を信じるところから始めれば、社会はより良くなっていくような気がします。素晴らしい本でした。
2021年の総括は以上です。気が向いたら今後も読書録の原文を投稿していきます。来年は何を読みましょうか。来年も良い本に出会い、また一つ人生が豊かになることを祈って筆を置きたいと思います。